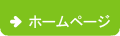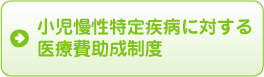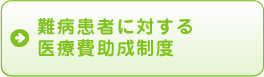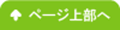平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が実施されました。
当サイトに記載されている医療費助成制度は、2023年7月時点の情報です。
事業の目的
子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く医療費負担が高額となります。小児慢性特定疾患治療研究事業は、児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助するものです。
対象年齢
18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童。自己負担額
(単位:円)
| 階層区分 |
階層区分の基準 (()内の数字は、 夫婦2人子1人世帯の場合 における年収の目安) |
患者負担割合:2割 | |||
| 自己負担上限額(外来+入院) | |||||
| 一般 | 重症 (※) |
人工 呼吸器等 装着者 |
|||
| 生活保護 | ー | 0 | 0 | 0 | |
| 低所得Ⅰ | 市町村民税非課税 (世帯) 本人年収〜80万円 |
1,250 | 1,250 | 500 | |
| 低所得Ⅱ | 市町村民税非課税 (世帯) 本人年収80万円超 |
2,500 | 2,500 | ||
| 一般所得Ⅰ | 市町村民税 課税以上 7.1万円未満 (約200万円〜約430万円) |
5,000 | 2,500 | ||
| 一般所得Ⅱ | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 (約430万円〜約850万円) |
10,000 | 5,000 | ||
| 上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 (850万円〜) |
15,000 | 10,000 | ||
| 入院時の食事療養費 | 1/2自己負担 | ||||
- ※重症:①高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、
医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、②現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。
手続きの流れ
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるためには、お住まいの都道府県庁、指定都市市役所、中核市市役所など(地域の保健福祉担当課や保健所など)への申請が必要です。小児慢性特定疾病の医療費助成の申請については以下のとおりです。
- ①小児慢性特定疾病指定医(※1)受診し、診断書の交付を受ける。
- ②診断書と必要書類を合わせて、保護者が都道府県庁などに医療費助成の申請をする。
◆主な必要書類:申請書、同意書、小児慢性特定疾病医療意見書、受診医療機関申請書、市町村民税(非)
課税証明書などの課税状況を確認できる書類、住民票、健康保険証の写し など - ③都道府県(または指定都市・中核市)で審査を行う。
- ④認定された場合、医療受給者証が保護者に送付される。
※認定されなかった場合は、その旨を通知する文書が送付されます。 - ⑤指定医療機関(※1)を受診し、治療を受ける。
- ※1:指定医・指定医療機関の制度を導入
新たな制度では、小児慢性特定疾病について診断を行う「指定医」や治療を行う「指定医療機関」を、都道府県知事または指定都市市長・中核都市市長が指定する制度が導入されます。
新しい制度の医療費助成を受けるためには、指定医による診断書が必要になります。
小児慢性特定疾病に対する医療費助成の対象となるのは、指定医療機関で受診した際の医療費です。
原則、指定医療機関以外の医療機関で受診した場合の医療費は、この制度の助成対象とはなりません。